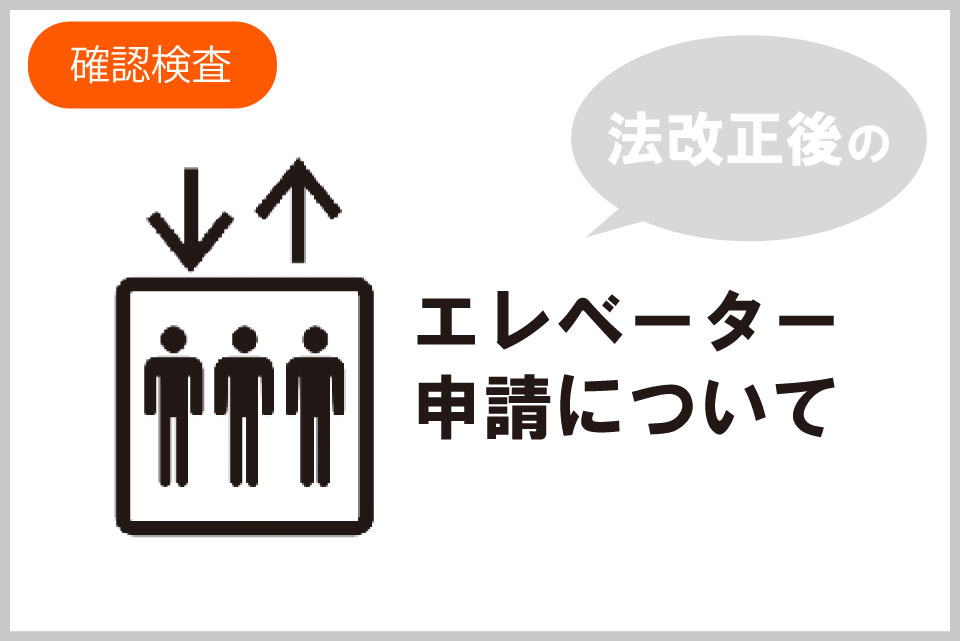いつもご利用ありがとうございます。設備課です。
2025年4月の建築基準法の改正により、エレベーターの申請も大きく変わりましたので、法改正後(令和7年4月以降)のエレベーター申請について解説いたします。
皆様の業務のお役に立てれば幸いです。
目次
建築基準法上の「昇降機」とは
昇降機の確認申請をする必要があるのか?というご質問をいただくことがありますので、改めて用語の定義等を説明いたします。
※詳しくは建築基準法第2条(用語の定義)の条文をご覧ください(e-GOV法令検索ページ参照)
まず、建築基準法第2条第一号で、「建築物」の中に「建築設備」が含まれます。
次に、建築基準法第2条第三号で、「建築設備」の中に「昇降機」が含まれます。
以上のことから、昇降機は建築基準法上、建築物と同じ扱いとなるため、原則確認申請が必要となります。
昇降機の申請方法
昇降機の確認申請は、設置予定の建築物によって下記のいずれかになります。
併願申請
建築物の一部として申請を行う方法です。建築物の確認申請時、申請図書の一部として昇降機図書の提出となります。この場合、建築物の確認申請・検査を行うため、「昇降機」単独の確認済証、検査済証はありません。
※新3号建築物(階数1かつ延べ面積200㎡以下)に設置する昇降機はすべて併願申請になります。
別願申請
昇降機のみで申請を行う方法です。主に工事着工中の建築物(建築物確認済証交付済)や既存建築物内に設置する場合に該当します。昇降機のみの確認申請となるため、昇降機の申請図書一式の提出となります。この場合、「昇降機」単独の確認済証、検査済証が発行されます。
建築物の確認申請を行う時点では昇降機の仕様やメーカーが決定していないことが多いため、別願申請での提出が一般的です。
ただし、別願申請ができない場合があります。詳しくは下記をご覧ください。
ホームエレベーター、小規模建築物に設置するエレベーター申請の注意点について
上記でエレベーターの確認申請の方法についてお伝えしました。そのうち、ホームエレベーター、小規模建築物に設置するエレベーターの申請時にご注意いただきたい告示(以下、新告示)があります。
●新告示 <令和6年9月9日 国土交通省告示第1148号>(令和7年4月1日施行)
確認等を要しない人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないエレベーターを定める件
< 告示本文 >
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第146条第1項第一号(e-GOV法令検索ページ参照)の規定に基づき、確認等を要しない人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないエレベーターを次のように定める。
建築基準法施行令第 146 条第 1 項第一号に規定する人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないエレベーターは、次に掲げるものとする。
一 籠が住戸内のみを昇降するもの
二 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第二号に掲げる建築物(階数が3以上であるもの、延べ面積が500㎡を超えるもの及び高さが16mを超えるものを除く。)に設けるもの
※上記第一号、第二号はいずれかに該当するもの(参照:令和6年9月9日パブリックコメントNo.1)
< 解 説 >
建築基準法施行令第146条は「確認等を要する建築設備」を、第1項第一号ではエレベーター及びエスカレーターで確認等が必要な場合を定めています。新告示は、上記施行令の除外規定「国土交通大臣が定めるもの=人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれが少ないもの」として下記の①②を定めています。
① 住宅内、住戸内のみを昇降するエレベーター(建築物種別、規模は不問)
② 法第6条第1項第二号の建築物で「階数2以下」「延べ面積500㎡以下」「高さ16m以下」
の3つの条件すべてにあてはまる建築物に設置するエレベーター
①また②に該当する場合、別願申請はできません。
建築基準法にてエレベーターとして定義されているもの(エレベーター(定員等不問)、段差解消機、いす式階段昇降機など)は、新告示に該当する場合、別願申請ができません。
建築物の確認申請が行われる場合(建築物の新築や増築に伴う設置等)、併願申請になります。
一方、建築物の確認申請が行われない場合(既存建築物内に設置する場合等)、新告示に該当すれば別願申請ができない、即ち申請不要となります。
今回の法改正は、既存建築物内への後付けの申請等に対しての措置が主となります。
注意点として、法第6条第1項第一号(別表第1(い)欄に掲げる用途の特殊建築物でその用途の床面積の合計200㎡超)の建築物に設置するエレベーターは、住宅内・住戸内のみを昇降するエレベーターを除き、別願申請になります。
建築物に係る防火関係規制の見直し等について(令和7年11月1日施行)
2025年(令和7年)8月29日に、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定、同年11月1日に施行されました。今回の改正は、建築物における木材利用のさらなる促進を目的とし、防火や避難に関する規制の一部が見直されています。
その中のひとつに、エレベーターや小荷物専用昇降機の規制範囲の変更がありました。
エレベーター・小荷物専用昇降機の規制範囲の変更
今回の改正により、建築基準法の規制対象となる昇降機の範囲が見直しがあり、労働安全衛生法で定義される「簡易リフト」が、建築基準法上の規制対象外となりました。
※建築基準法施行令第129条の3(e-GOV法令検索ページ参照)における「エレベーター」および「小荷物専用昇降機」の定義から除外されました。
労働安全衛生法における「簡易リフト」とは?
「簡易リフト」とは、次の条件を満たすエレベーターを指します。
・特定事業の事業場などに設置されるもの
※特定事業の事業場:労働基準法 別表第一の1~5(e-GOV法令検索ページ参照)
・かごの床面積が1㎡以下 または かごの天井高さが1.2m以下のもの
・荷物のみを運搬することを目的としたもの
建築基準法での「昇降機」とは定義が異なります。
建築確認申請時の注意点
例えば、簡易リフト付きの上記事業場等の新築の建築確認申請を行う場合、「当該設備が簡易リフトであることを確認するための図面」の提出を求められるケースがございます。
そのため、事前に図面等の準備をおすすめします。
詳しくは国土交通省ホームページ「建築物に係る防火関係規制の見直し等について」をご覧ください。
最後に
エレベーター含め、昇降機を設置する際には、原則として確認申請が必要です。
その中で、新告示、ならびに政令に伴う変更点について、申請前にご確認ください。
建築物が新築・増築などで確認申請を行う場合のエレベーター設置の申請
併願申請となる場合、建築物の確認申請時に昇降機図書の提出となります。完了検査時に、建築物とあわせて昇降機の検査も行いますので、昇降機メーカーとのご調整をお願いいたします。
建築物の申請者様は、
・建築物の確認申請時:仕様確定の上での昇降機図書の提出
・建築物の完了検査時:昇降機メーカーとの日程調整・予約・検査申請
を行っていただくようお願いいたします。
別願申請となる場合、昇降機の確認申請時に建築物の意匠図(案内図、配置図、各階平面図)等が必要です。昇降機メーカーが確認申請を行う際、建築物の確認申請(計画変更をおこなっていれば計画変更)時の上記意匠図等のご提供をお願いいたします。
完了検査時につきましても、建築物と昇降機の完了検査の実施日等、ご調整をお願いいたします。
労働安全衛生法で定義される「簡易リフト」について
令和7年11月1日に施行された「建築基準法施行令の一部を改正する政令」において、建築基準法の規制対象とするエレベーター、小荷物専用昇降機の範囲の変更がありました。
以上、法改正後のエレベーター申請における変更点と注意点を紹介いたしました。
今後も皆さまのお役に立てる情報を発信してまいります。
それでは次回もよろしくお願いいたします。
■申請はSpeedyが便利です
Speedyなら申請書を最新書式に自動反映!
確認検査申請以外にも性能評価・長期優良・省エネ適判など各種申請もご利用いただけます。
その他の機能も充実!詳しくはSpeedy特別ページまで
■過去に掲載した現場で差がつく!実務ヒント集もぜひご覧ください